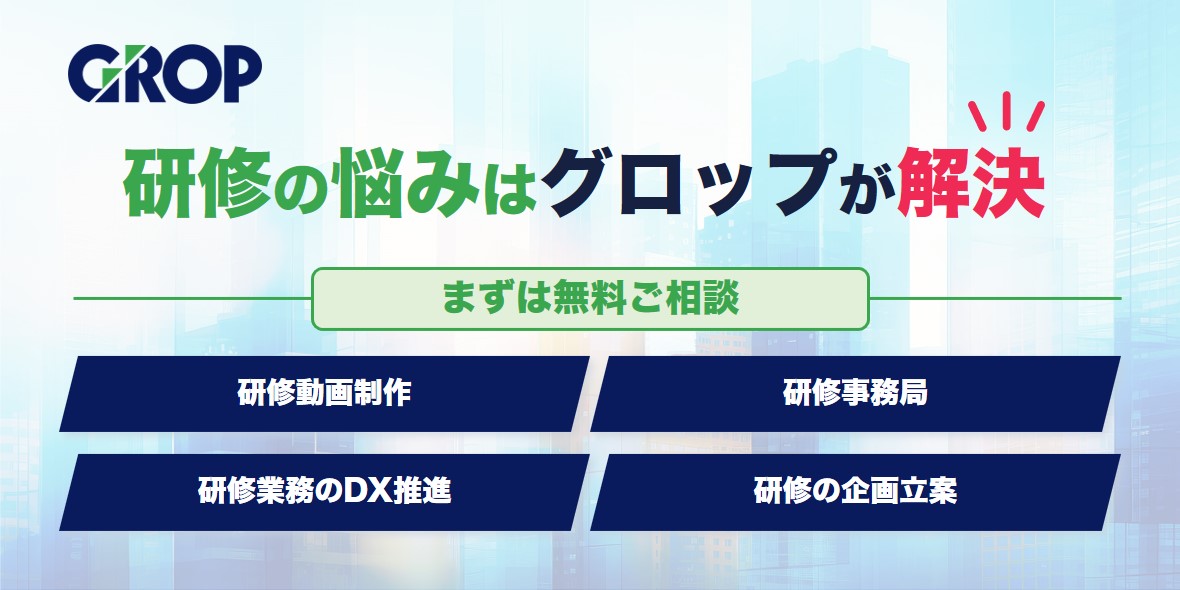社員研修に使える助成金制度とは?利用するメリットや申請の流れも解説
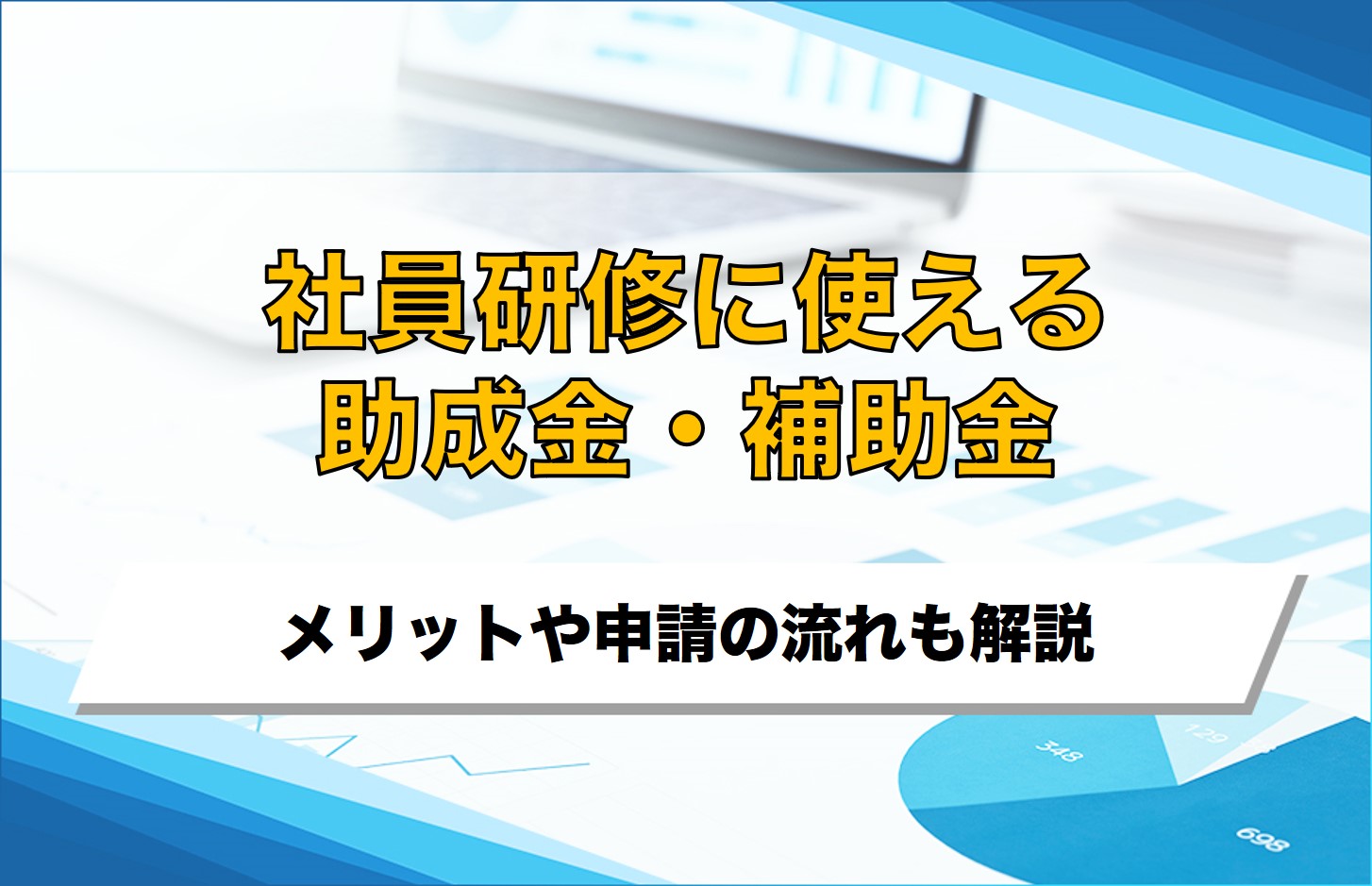
「社員研修に使える助成金とは?」
「補助金を使うメリット・デメリットは?」
研修に助成金を活用すれば、費用の負担を抑えながら人材育成に取り組めます。新入社員研修からスキルアップ研修、リスキリングまで幅広く対象となり、企業にとって大きなメリットです。
しかし「どの研修が対象になるのか分からない」「申請の手続きが複雑そうで不安」といった声も多く、せっかくの制度をうまく活用できていない企業も少なくありません。
そこで本記事では、研修に利用できる助成金の仕組みやメリットをわかりやすく解説し、申請時に注意すべきポイントについてもご紹介します。
助成金を活用した研修ならグロップ
毎年実施する入社研修などの教育は、繰り返し利用できてコスパに優れた動画がおすすめです。助成金を活用すれば、制作費用は最大75%削減できます。グロップなら専門サービス「まなびに+」を運用しており、1本8.5万円の低価格で制作を依頼できます。
目次
社員研修に利用できる助成金・補助金制度とは

国や自治体では、社員研修に利用できる助成金制度を設けています。企業による人材育成を促進し、労働者のキャリア形成やスキルアップを支援するためです。
企業にとっても「研修コストの軽減」「人材定着」「生産性向上」といったメリットがあります。代表的な制度としては、厚生労働省による「人材開発支援助成金」や各自治体で独自に実施しているものがあります。
例えば、スキルアップのeラーニングなら最大75%の経費助成が受けられます。グロップなら助成金を利用したい企業向けにAI・DXの研修動画を提案しているので、ぜひご活用ください。
人材開発支援助成金(厚生労働省)

人材開発支援助成金の6コース
- 人材育成支援コース
- 教育訓練休暇等付与コース
- 人への投資促進コース
- 事業展開等リスキリング支援コース
- 建設労働者認定訓練コース
- 建設労働者技能実習コース
人材開発支援助成金は、企業が社員に研修や訓練を行う際に、その経費や研修中の賃金の一部を国が助成する制度です。社員のスキルアップやキャリア形成を後押しし、企業の生産性向上につなげることを目的としています。
対象となる研修は幅広く、新入社員研修や資格取得研修など職務に直結するものはもちろん、新規事業に必要な知識や技術を学ぶリスキリング研修も含まれます。人材開発支援助成金のメインとなる1~4コースを中心に、それぞれ解説していきます。
1.人材育成支援コース
人材育成支援コースの対象となる訓練メニュー
| 訓練タイプ | 条件の概要 |
|---|---|
| 人材育成訓練 | OFF‑JTを10時間以上実施した場合 |
| 認定実習併用職業訓練 | OJTとOFF‑JTを組み合わせた訓練で、中核人材の育成を目的とする場合 |
| 有期実習型訓練 | 有期契約労働者を正規社員化する意図で、OJT+OFF‑JTを実施した場合 |
参考:厚生労働省「令和7年度版 人材育成支援コースのご案内」
企業が社員に職務に関連した知識・技能を習得させる訓練を行う際、その費用や研修中の賃金をサポートする助成制度です。新入社員研修から中堅社員の専門スキル、OJT・OFF‑JTの組み合わせまで、幅広く対応されています。
人材育成支援コースの支給額・助成率(中小企業の例)
| 訓練タイプ | 経費助成 | 賃金助成 (1人1時間あたり) | OJT助成 (1人1コースあたり) |
|---|---|---|---|
| 人材育成訓練 (正規) |
45% | 800円 | なし |
| 人材育成訓練 (非正規) |
70% | 800円 | なし |
| 認定実習併用職業訓練 | 45% | 800円 | 20万円 |
| 有期実習型訓練 | 75% | 800円 | 10万円 |
参考:厚生労働省「令和7年度版 人材育成支援コースのご案内」
上記は、中小企業の人材育成支援コースの支給額・助成率をまとめたものです。賃上げなどの条件を満たすと助成額が追加される可能性もあります。ちなみに、大企業の場合は経費助成率が30%、賃金助成は1人1時間あたり400円です。
2.教育訓練休暇等付与コース
教育訓練休暇等付与コースの対象となる訓練メニュー
| 訓練タイプ | 条件の概要 |
|---|---|
| 教育訓練休暇制度 | 3年間に5日以上の有給休暇を規定し運用 |
| 長期教育訓練休暇制度 | 30日以上の連続休暇を取得可能な制度 |
| 教育訓練短時間勤務等制度 | 短時間勤務または残業免除制度を活用した訓練対応 |
参考:厚生労働省「令和7年度版 教育訓練休暇等付与コースのご案内」
企業が有給の教育訓練休暇制度を導入し、社員が実際に休暇を取得した場合、その制度導入費用や休暇中の賃金の一部を国が助成します。制度は、短期間から30日以上の長期間の休暇まで複数タイプがあり、目的や職場状況に応じて選択できます。
教育訓練休暇等付与コースの支給額・助成率(中小企業の例)
| 訓練タイプ | 経費助成 | 賃金助成 (1人1時間あたり) |
|---|---|---|
| 教育訓練休暇制度 | 30万円 | なし |
| 長期教育訓練休暇制度 | 20万円 | 1,000円 (最大1,600時間) |
| 教育訓練短時間勤務等制度 | 20万円 | なし |
参考:厚生労働省「令和7年度版 教育訓練休暇等付与コースのご案内」
上記は、中小企業の教育訓練休暇等付与コースの支給額・助成率をまとめたものです。1事業所1年度当たりの限度額は設定されていません。ただし「教育訓練休暇制度」については、1事業主に対して1度限り助成金30万円が支給されます。
3.人への投資促進コース
人への投資促進コースの対象となる訓練メニュー
| 訓練タイプ | 条件の概要 |
|---|---|
| 高度デジタル人材訓練/成長分野等人材訓練 | DXや高度ITスキル訓練、大学院での研修など |
| 情報技術分野認定実習併用職業訓練 | IT分野未経験者向けOFF‑JTとOJTを組み合わせた訓練 |
| 定額制訓練 | 定額で受け放題のeラーニングなど |
| 自発的職業能力開発訓練 | 社員が自主的に受講する研修費(会社負担分) |
| 長期教育訓練休暇等制度 | 長期休暇や短時間勤務制度を設け、学習に専念できる環境の導入 |
参考:厚生労働省「令和7年度版 人への投資促進コースのご案内」
企業が社員への教育・研修に「投資」することを促進するために設けられた制度です。デジタル化に対応したスキル習得や自己啓発を支援する先進的な内容となっています。
人への投資促進コースの支給額・助成率(中小企業の例)
| 訓練タイプ | 経費助成 | 賃金助成 (1人1時間あたり) | OJT助成 |
|---|---|---|---|
| 高度デジタル人材訓練/成長分野等人材訓練 | 75% | 1,000円 | なし |
| 情報技術分野認定実習併用職業訓練 | 60% | 800円 | 20万円 |
| 定額制訓練 | 60% | なし | なし |
| 自発的職業能力開発訓練 | 45% | なし | なし |
| 長期教育訓練休暇等制度 (30日以上の休暇取得) |
20万円 | 1,000円 | なし |
| 長期教育訓練休暇等制度 (所定労働時間の短縮) |
20万円 | なし | なし |
参考:厚生労働省「令和7年度版 人への投資促進コースのご案内」
上記は、中小企業の人への投資促進コースの支給額・助成率をまとめたものです。eラーニング及び通信制による訓練の場合、賃金助成はないので注意しましょう。
4.事業展開等リスキリング支援コース
事業展開等リスキリング支援コースの対象となる要件
- OFF-JT形式であること
- 実訓練時間が10時間以上であること
- 新規事業展開に必要な専門知識・技能※
- DX推進やグリーン・カーボンニュートラル化に関連する業務に必要な知識・技能※
参考:厚生労働省「令和7年度版 事業展開等リスキリング支援コースのご案内」
※3・4はいずれかを満たす訓練であればよい
企業が、新規事業展開やDX・グリーン/カーボンニュートラル化に伴い、社員に必要な専門知識や技能を習得させる訓練を支援する助成制度です。訓練にかかる経費や賃金の一部を支給して、リスキリングを促進します。
ただし、単なる自己啓発・モチベーションアップ研修や、趣味的要素が強く業務と直接関係ないものなどは対象外となるため注意しましょう。
事業展開等リスキリング支援コースの支給額・助成率(中小企業の例)
| 経費助成 | 75% |
|---|---|
| 賃金助成 (1人1時間あたり) | 1,000円 (最大1,200時間) |
参考:厚生労働省「令和7年度版 事業展開等リスキリング支援コースのご案内」
上記は、中小企業の事業展開等リスキリング支援コースの支給額・助成率をまとめたものです。eラーニングや通信制、定額制サービス、育児休業中の訓練も助成対象に含まれます。
これらは経費助成のみ(1人1月あたり2万円)となりますが、導入しやすい研修スタイルを支援する仕組みとして活用可能です。
【PR】助成金を活用した研修動画制作ならグロップ
| 特徴 | ・1本8.5万円から依頼できる ・費用のディスカウントあり ・外国語対応 |
|---|---|
| 得意ジャンル | ・研修動画 ・マニュアル動画 ・教材用動画 |
| 費用 | テキスト画像使用 :8.5万円 キャライラスト使用:24.5万円 撮影あり :36.5万円 ▶料金例の詳しい解説はこちら |
| 公式サイト | ▶グロップの研修動画サービス |
グロップでは助成金を活用した研修のサポートを積極的に行っています。主に、AIやDXの研修動画を内容の相談から制作まで請け負います。
「助成金を利用できる研修内容ができるか不安」「スキルアップの研修をしたいけど自社にふさわしい人材がいない」などでお困りなら、ぜひご相談ください
5.建設労働者認定訓練コース
建設業界の人材育成を支援する制度です。建設関連の認定職業訓練や指導員訓練を実施した場合、訓練にかかる経費の一部や、有給で受講させた際の賃金の一部が助成されます。長期的な技能習得や体系的な人材育成を支援が目的です。
6.建設労働者技能実習コース
建設業界で働く建設労働者に対し、有給で技能実習を受けさせた場合に、その訓練にかかった経費や賃金の一部が助成される制度です。即戦力となる技能や安全確保に必要な技能を短期的に習得させます。
地方自治体による独自の助成制度

各自治体でも独自の助成制度を設けており、社員研修や人材育成の費用を助成しています。こうした制度は国の「人材開発支援助成金」と併用できる場合もあり、より負担を抑えて研修を実施できるのが特徴です。
対象経費や上限額は自治体ごとに異なり、毎年度の予算に基づいて運用されているため、早めに情報収集しておきましょう。また、併用を検討する際は、事前に労働局や自治体に確認するのが安心です。
社員研修に助成金を利用するメリット

コスト負担を軽減できる
社員研修は企業にとって欠かせない取り組みですが、研修費や外部講師への依頼料、社員を拘束する時間にかかる人件費など、どうしても大きなコストが発生します。こうした負担を理由に研修を見送ってしまう企業も少なくありません。
その点、助成金を活用すれば研修費用の一部や研修中の賃金の一部が支給されるため、企業のコスト負担を大幅に抑えられます。限られた予算の中でも質の高い研修を導入しやすくなり、結果として人材育成を継続的に進めやすくなるのです。
幅広い研修に対応している
助成金を活用する大きなメリットのひとつは、幅広い研修に対応していることです。新入社員を対象とした基礎研修や、若手・中堅社員のスキルアップ研修はもちろん、資格取得や専門スキルの習得を目的とした研修まで支援の対象に含まれます。
このように多様な研修がサポートされることで、自社の課題や人材育成の方針に合わせて柔軟に制度を活用でき、より効果的な人材育成が可能になります。
社員が学ぶ機会を安定的に確保できる
社員研修は、コストの負担から継続が難しくなることもあります。しかし、助成金を活用すれば費用を抑えられ、社員に学ぶ機会を安定して確保できます。
継続的な研修が可能になることで、社員の成長を後押しし、組織全体の力を高めることにつながります。
社員研修に助成金を利用するデメリット

助成金が支給されるまで時間がかかる
助成金は支給されるまで時間がかかります。研修後すぐに資金が入るわけではなく、書類の提出や審査を経て支給が決まるまでに数ヶ月を要する場合が多いです。
そのため、研修費用は一時的に自社で立て替える必要があり、資金繰りに余裕がない企業には負担となることがあります。
全ての研修で利用できるわけではない
助成金は幅広い研修を対象としていますが、すべての研修で利用できるわけではありません。業務に直接関係しない内容や、趣味的な研修は対象外となります。
また、研修の方法や時間数などにも条件が設けられており、基準を満たさなければ助成の対象にならないため注意しましょう。
申請手続きが複雑で手間がかかる
助成金を利用する際に避けられないのが、申請手続きです。計画書や申請書類を揃え、研修内容や実施状況を証明する資料を提出しなければならず、専門的な知識がないと手間取ることもあります。
もし不安がある場合は、申請サポートを行っている研修代行会社に依頼するのも一つの方法です。グロップでは研修動画の制作から申請サポートまで可能ですのでぜひご相談ください。
人材開発支援助成金の申請の流れ

- 事前準備
- 訓練計画の届け出
- 訓練の実施
- 支給申請
- 審査・支給
人材開発支援助成金の申請の流れを紹介します。必要書類などはコースによって異なりますので、厚生労働省のパンフレットや公式ページを必ず確認しましょう。
1.事前準備
助成金を利用するには、事業所ごとに「職業能力開発推進者」を選任しておく必要があります。一般的に選任されるのは、人事や労務に携わっている社員です。研修や人材育成に関する知識を持ち、労働局とのやり取りを行いやすい立場にあるからです。
次に、職業能力開発計画の策定・周知を行います。計画には、実施する研修の内容や対象者、期間などを明記し、社員にきちんと伝えておくことが求められます。
2.訓練計画の届け出
訓練開始日の1ヶ月前までに「訓練計画届」など必要書類を管轄の労働局へ提出します。書類には、訓練の実施内容、対象者、日程、費用の内訳などを記載します。この段階で不備があると助成金が受けられないため、特に注意が必要です。
3.訓練の実施
計画届に基づいて、研修を実施します。出席簿やカリキュラム、研修中の賃金支払い記録など、証拠資料を必ず保管しておきます。
4.支給申請
訓練終了日の翌日から2ヶ月以内に「支給申請書」を労働局へ提出します。必要な書類は訓練メニューによって変わるため、あらかじめ確認しておきましょう。
5.審査・支給
労働局による審査が行われ、不備がなければ助成金が支給されます。支給までには数ヶ月かかることもあるため、一度は自社で研修費用を立て替えが必要です。
助成金の対象となる研修例

社内研修(OJT・OFF-JT)
OJTは実際の業務を通してスキルを身につける方法で、日常の業務と直結した実践的な学びが得られるのが特長です。
一方、OFF-JTは職場を離れ、講義や演習を通じて体系的に知識や技術を習得する形式です。社内講師による集合研修や外部講師を招いたセミナーもこれに含まれます。
外部セミナー・講習会
社外で実施されるセミナーや講習会に参加することで、最新の知識や専門的なスキルを体系的に学べます。社内では得にくい実践的なノウハウを短期間で習得できるのが大きな魅力です。
外部研修を取り入れることで、社員が社外の人材と交流し、新しい視点や刺激を得られる点もメリットです。
長期教育訓練休暇を利用した研修
一定期間まとまった休暇を取得し、その間に集中的に学習や研修に取り組む仕組みです。例えば、30日以上の休暇を活用して専門的なスキルを磨いたり、大学や専門機関で高度な知識を学んだりするケースが想定されます。
長期にわたって学習の時間を確保できるため、短期間の研修では身につけにくい知識や技能を体系的に習得できるのが特長です。
通信教育
社員が自宅や職場など場所を問わず学習できる通信教育は、業務の合間や空き時間を活用しやすく、継続的なスキルアップに適しています。資格取得や語学、ITスキルなど幅広い分野を学べる点も魅力で、個々のキャリア形成を柔軟に支援できます。
企業にとっても、社員一人ひとりの学習スタイルに合わせた教育が可能となり、働きながら成長できる環境づくりにつながります。
eラーニング・動画研修
インターネットを通じて学習できるeラーニングは、時間や場所を選ばず受講できます。動画研修も同様に、繰り返し視聴しながら理解を深められる点で効果的です。
また、最新の教材をオンラインで導入すれば、常に新しい知識を学べる環境を整えられます。こうした研修スタイルは、働き方の多様化に対応しつつ、コストを抑えたい企業におすすめです。
【PR】助成金を活用した研修動画制作ならグロップ
| 特徴 | ・1本8.5万円から依頼できる ・費用のディスカウントあり ・外国語対応 |
|---|---|
| 得意ジャンル | ・研修動画 ・マニュアル動画 ・教材用動画 |
| 費用 | テキスト画像使用 :8.5万円 キャライラスト使用:24.5万円 撮影あり :36.5万円 ▶料金例の詳しい解説はこちら |
| 公式サイト | ▶グロップの研修動画サービス |
グロップでは助成金を活用した研修のサポートを積極的に行っています。主に、AIやDXの研修動画を内容の相談から制作まで請け負います。
「助成金を利用できる研修内容ができるか不安」「スキルアップの研修をしたいけど自社にふさわしい人材がいない」などでお困りなら、ぜひご相談ください
人材開発支援助成金に関するよくある質問

どんな企業でも利用できる?
基本的に雇用保険に加入している企業であれば利用可能です。ただし、労働保険料を滞納している場合や過去に不正受給があった場合は対象外となります。
助成金はいつ支給される?
研修を実施した後に申請し、審査を経て数ヶ月後に振り込まれます。
どれくらい助成される?
助成率はコースや企業規模によって異なります。中小企業で最大75%、大企業でも60%程度が助成される場合があります。
助成金は併用できる?
国の助成金は原則として同じ訓練に対して複数を併用することはできません。ただし、国の制度と自治体独自の補助金を組み合わせられるケースはあります。
まず何から始めればいい?
まずは「どの研修を実施したいのか」を整理し、その研修がどの助成コースに当てはまるかを確認します。その上で、労働局や専門家に相談するとスムーズです。
不支給になるケースはある?
書類作成や要件確認の不備による不支給リスクがあります。社会保険労務士や申請サポート付き研修サービスを活用しましょう。
まとめ:社員研修は助成金を賢く利用すべき
社員研修はコストがかかりますが、助成金を活用すれば負担を抑えて継続的に実施できます。人材育成を「投資」と捉え、助成金を賢く使うことで、企業の成長につながる研修が実現できるでしょう。
【PR】助成金を活用した研修動画制作ならグロップ
グロップでは助成金を活用した研修のサポートを積極的に行っています。主に、AIやDXの研修動画を内容の相談から制作まで請け負います。
「助成金を利用できる研修内容ができるか不安」「スキルアップの研修をしたいけど自社にふさわしい人材がいない」などでお困りなら、ぜひご相談ください。