特定技能外国人を採用する流れは?採用にかかる費用相場や注意すべきポイントを解説
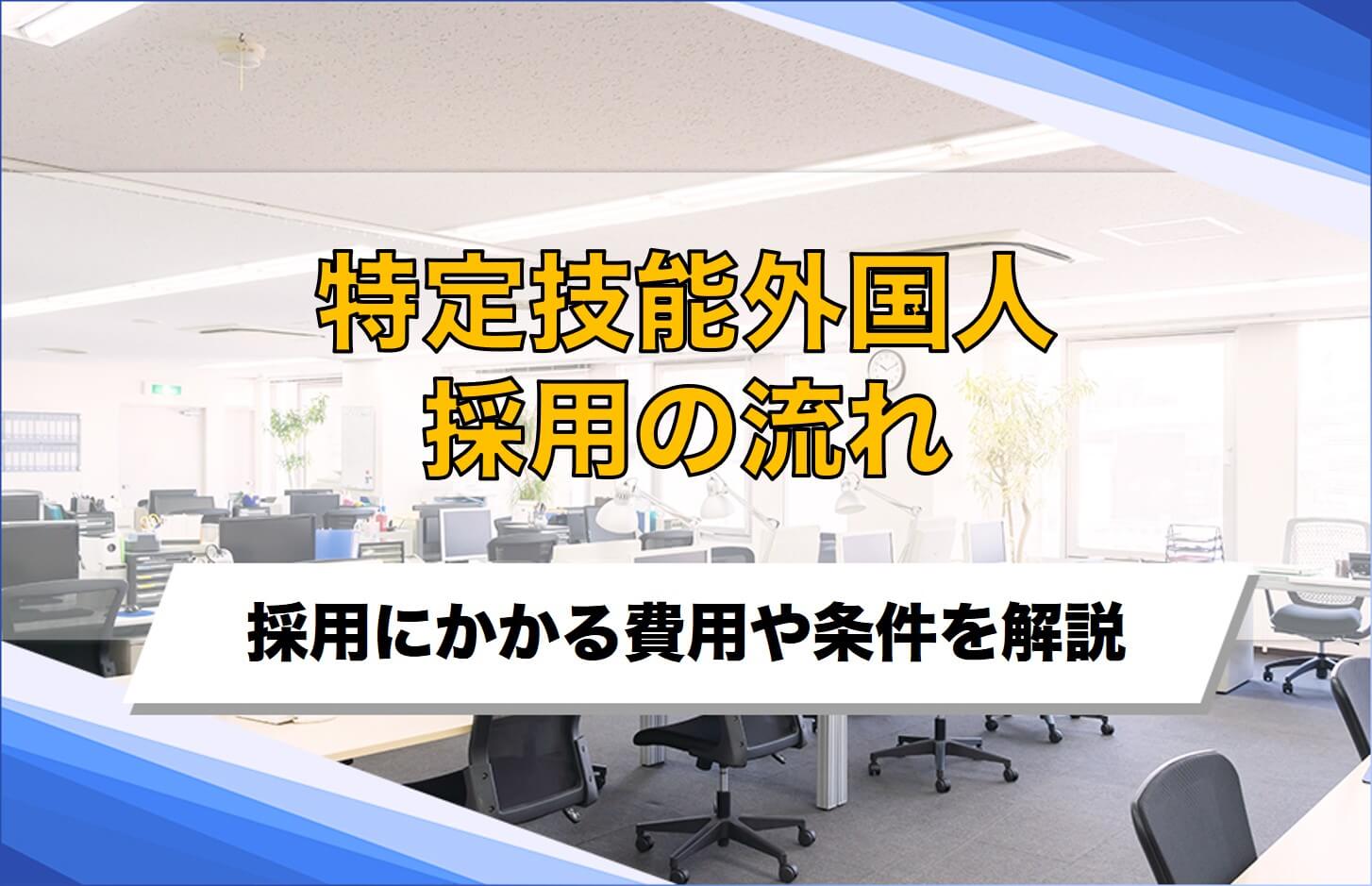
「特定技能外国人を採用する流れは?」
「特定技能を採用するための費用相場が知りたい」
特定技能制度は、人手不足が深刻な産業分野で外国人が働けるように設けられた新しい在留資格です。採用が難航している企業は、導入を考えているケースも多いのではないでしょうか。
しかし「どういった制度なのかイマイチわからない」「手続きが複雑そう」と不安に思いますよね。
そこで本記事では、特定技能外国人を採用する流れや、必要な費用について解説します。採用時に注意すべきポイントも紹介するので、ぜひ参考にしてください。
目次
特定技能とは

特定技能とは、2019年4月に新設された在留資格のひとつで、人手不足が深刻な産業分野で外国人が働けるように設けられた新しい在留資格です。
従来は専門性の高い「高度人材」や、研修を目的とする「技能実習」が中心でしたが、その中間にあたる「即戦力人材」を受け入れるために作られました。
特定技能1号と2号の主な違い
| 項目 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
|---|---|---|
| 主な対象 | 一定の日本語力と基礎〜中級の技能を持つ即戦力 | より熟練した高度な技能を持つ人材 |
| 在留期間 | 最長5年(更新可・通算上限5年) | 上限なし(更新により長期在留が可能) |
| 家族帯同 | 不可 | 可(配偶者・子) |
| 受け入れ企業の支援義務 | 生活・就労支援が義務(登録支援機関へ委託可) | 1号のような生活支援義務は原則なし |
| 主な取得要件 | 技能試験+日本語試験(分野規定に従う) | より高い技能要件(分野ごとの基準に従う) |
特定技能1号と2号の主な違いは、求められる技能の水準や在留期間、家族の帯同可否、企業の支援義務、そして取得要件にあります。1号は一定の日本語力と基礎的な技能を持つ即戦力人材を対象としており、在留期間は最長5年までです。
家族の帯同は認められず、受け入れ企業には生活支援や職場定着のための支援義務があります。取得には、技能試験と日本語試験に合格する必要があります。
一方の2号は、より高度で熟練した技能を持つ人材を対象としており、在留期間の上限がなく、家族の帯同も可能です。企業側の生活支援義務はなく、取得要件は分野ごとに定められた高度な技能基準を満たす必要があります。
特定技能の対象となる16分野
| 介護 | ビルクリーニング |
| 工業製品製造業 | 建設 |
| 造船・船用工業 | 自動車整備 |
| 航空 | 宿泊 |
| 自動車運送業 | 鉄道 |
| 農業 | 漁業 |
| 飲食料品製造業 | 外食業 |
| 林業 | 木材産業 |
出典:出入国在留管理庁
特定技能制度で対象となる分野は全部で16あります。これらは、人手不足が深刻な業種を中心に設定されており、主に「人の手による技能や専門知識を必要とする仕事」が対象です。
具体的には、介護分野をはじめ、ビルクリーニング、工業製品や飲食料品といった製造系のほか、建設、航空、宿泊、農業、漁業、外食業などが含まれます。さらに、近年は鉄道分野や林業分野も追加され、幅広い産業で外国人材の受け入れが進んでいます。
特定技能外国人を採用するための受入れ要件

特定技能外国人を採用するには、外国人本人だけでなく、受け入れる企業側も一定の基準を満たす必要があります。これは、外国人材が安心して働ける環境を整えるために定められた制度上の要件です。
特定技能雇用契約が満たすべき基準
| 1 | 分野省令で定められた技能を必要とする業務に従事させること |
|---|---|
| 2 | 勤務時間は、同じ企業で働く日本人社員と同等の所定労働時間とすること |
| 3 | 給与は、日本人が同じ業務に従事する場合と同等以上の金額とすること |
| 4 | 国籍を理由に、報酬の決定や教育訓練、福利厚生施設の利用などで差別的な扱いをしないこと |
| 5 | 外国人が一時帰国を希望した場合には、休暇を取得できるようにすること |
| 6 | 労働者派遣として受け入れる場合は、派遣先や派遣期間を明確に定めておくこと |
| 7 | 外国人が帰国旅費を負担できないときは、企業が負担し、契約終了後に円滑に出国できるよう必要な対応を行うこと |
| 8 | 外国人の健康状態や生活状況を把握し、必要に応じて適切な支援を行うこと |
| 9 | 各分野ごとに定められた特有の基準(分野所管省庁の告示)に適合していること |
参考:出入国在留管理庁
企業は適正な雇用契約を結んでいることが前提です。給与や労働時間、休日などの条件が日本人と同等以上でなければなりません。
受入れ機関自体が満たすべき基準
| 1 | 労働法、社会保険、税金などに関する法令を守っていること |
|---|---|
| 2 | 過去1年以内に、特定技能外国人と同じ業務に就く労働者を、企業側の都合で解雇していないこと |
| 3 | 過去1年以内に、企業の管理体制の不備などが原因で、特定技能外国人が行方不明になっていないこと |
| 4 | 過去5年以内に、出入国管理法や労働関係法令などに違反していないこと |
| 5 | 特定技能外国人の仕事内容などを記した文書を作成し、雇用契約が終了した日から少なくとも1年間は保管しておくこと |
| 6 | 外国人が保証金などを徴収されていることを知りながら雇用契約を結んでいないこと |
| 7 | 企業側が、外国人との間で違約金などを定める契約を結んでいないこと |
| 8 | 外国人への支援にかかる費用を、直接的にも間接的にも外国人本人に負担させないこと |
| 9 | 労働者派遣として受け入れる場合は、派遣元がその分野の業務を適切に行える事業者であり、派遣先も1〜4の基準を満たしていること |
| 10 | 労災保険への加入や、そのための届出を適切に行っていること |
| 11 | 雇用契約を継続して履行できる体制が、社内に整っていること |
| 12 | 給与は、預貯金口座への振込など、適切な方法で支払うこと |
| 13 | 各分野ごとに定められた特有の基準(分野所管省庁の告示)を満たしていること |
参考:出入国在留管理庁
労働関係法令や社会保険などを遵守していることも求められます。また、外国人が従事する業務内容が特定技能制度で定められた分野に該当していることが必要です。対象外の業務を行わせることは認められていません。
受入れ機関自体が満たすべき基準(支援体制関係)
| 1 | 1-1~1-3のいずれかに該当していること |
|---|---|
| 1-1 | 過去2年間に、中長期在留者(就労資格のみ)の受け入れや管理を適切に行った実績があり、さらに、役職員の中から支援責任者および支援担当者(事業所ごとに1名以上)を選任していること ※支援責任者と支援担当者は兼任しても構いません |
| 1-2 | 役職員の中に、過去2年間に中長期在留者(就労資格のみ)の生活相談などに従事した経験を持つ者がいて、その中から支援責任者および支援担当者を選任していること |
| 1-3 | 1-1または1-2と同等の能力を持ち、支援業務を適切に実施できる者が役職員におり、その中から支援責任者および支援担当者を選任していること |
| 2 | 外国人が十分に理解できる言語で支援を行える体制を整えていること |
| 3 | 支援の実施状況を記録した文書を作成し、雇用契約終了日から1年以上保管しておくこと |
| 4 | 支援責任者および支援担当者が、中立的な立場で支援計画を実施でき、かつ欠格事由に該当していないこと |
| 5 | 過去5年以内に、支援計画に基づく支援を怠った事実がないこと |
| 6 | 支援責任者または支援担当者が、外国人本人およびその上司などの監督者と、定期的に面談を行える体制を整えていること |
| 7 | 各分野において定められた特有の基準(分野所管省庁の告示)に適合していること |
参考:出入国在留管理庁
企業には支援体制の整備義務があります。生活や職場への定着を支援するために、住居の確保や日本語学習支援、相談対応などを行う体制を持つことが求められます。これらを自社で行えない場合は、出入国在留管理庁に認可された登録支援機関に委託が可能です。
特定技能採用のチェックリスト
| 項目 | やること |
|---|---|
| 1.業務内容の要件チェック |
・自社の業務が特定技能で認められているか確認 ・業務内容が単純作業に偏っていないか精査 |
| 2.事業所の要件チェック |
・就業場所が特定技能の受入要件を満たしているか確認 ・必要な設備や体制が整っているか確認 |
| 3.人材の要件チェック |
・技能試験・日本語試験の合格状況を確認 ・技能実習2号修了者の免除条件も確認 |
| 4.求人票の作成 |
・1〜3を満たす内容で求人票を作成 ・業務内容・給与・勤務時間・残業条件を明記 |
| 5.内定 |
・内定通知の発行 ・内定承諾の取得 ・雇用する人材を正式決定 |
| 6.支援計画の作成(必須) |
・住居確保 ・役所手続き同行 ・生活オリエンテーション ・日本語学習支援 ・相談窓口の設置 ・月1回の面談設定 |
| 7.事前ガイダンスの実施(必須) |
・労働条件の説明 ・業務内容の説明 ・生活ルールの説明 ・勤務上の注意点を共有 |
| 8.協議会への入会 |
・分野別協議会に加入 ・必要書類の提出 |
| 9.ビザ申請 |
・必要書類の収集(雇用契約書、企業書類、試験合格証など) ・申請書の作成 ・入管へ申請(認定 or 変更) |
| 10.入社前後の支援 |
・銀行口座開設 ・携帯契約 ・住居契約 ・通勤経路説明 ・初日オリエンテーション |
| 11.雇用後の手続き |
・社会保険・雇用保険の加入 ・労働条件通知書の交付 ・勤怠・残業管理体制の整備 |
| 12.四半期ごとの報告(義務) | ・特定技能外国人の状況を入管へ報告(年4回) |
| 13.ビザ更新 |
・在留期限前に更新書類を準備 ・更新申請を実施 |
| 14.支援計画の実施(随時) |
・月1面談の継続 ・生活・仕事の相談対応 ・日本語学習支援 ・トラブル対応 ・定着フォロー |
特定技能外国人の採用でやるべきことをチェックリストにまとめました。初めての企業でも、このリストを使えば迷わずに準備を進められます。
また、登録支援機関を利用すれば、内定後の作業は委託可能です。自社で対応する部分と外部に任せる部分を整理し、効率的に受け入れ体制を整えましょう。
特定技能外国人の採用までの流れ

- 受入れ要件の確認
- 求人・募集・面接
- 雇用契約の締結
- 支援計画の準備
- 在留資格の申請・許可
- 入社・定着支援
1.受入れ要件の確認
特定技能外国人を採用するには、まず企業が「受入れ機関」としての条件を満たしている必要があります。条件を満たさないと、特定技能外国人の雇用契約を締結しても「在留資格認定」が下りないため、最初に確認しておくことが重要です。
2.求人・募集・面接
特定技能外国人の募集方法
- 人材紹介会社
- 求人広告サイト
- スカウトサイト
- SNS
特定技能人材の募集方法は主に4つです。人材紹介会社や登録支援機関を通じて行うのが一般的ですが、ハローワーク・求人広告・スカウトサイトなどを利用する方法もあります。以下でそれぞれ解説します。
人材紹介会社
最も利用されているルートが人材紹介会社を通じた採用です。希望条件を伝えるだけで企業に代わって採用活動を行うため、特定技能に不慣れな企業でもスムーズに採用を進められます。
国内外のネットワークをもつ紹介会社であれば、候補者の母数も多く、短期間で人材を確保しやすい点が強みです。
求人広告サイト
外国人向け求人広告サイトに求人を掲載し、応募を待つ方法です。求人掲載のコストを抑えながら、多くの求職者に情報を届けることができます。特に日本国内にいる求職者からの応募が集まりやすい傾向があります。
書類選考や面接日程の設定は企業側が主体となるため、自社で採用をコントロールしたい企業に向いている採用チャネルです。
スカウトサイト
スカウトサイトでは、企業側が気になる求職者に直接アプローチできます。日本で就労を希望する外国人の登録が多く、マッチング精度が高いのが特徴です。
求めるスキルや日本語レベルを持つ人材をピンポイントで探しやすいため、早期に即戦力を確保したい企業にとって有効な手段となります。成功報酬型のサービスが多く、無駄な採用コストが発生しにくい点もメリットです。
SNS
海外ではSNSが主要な就職情報源になっている地域も多く、特定技能を扱う企業や団体がSNSを通して募集するケースも増えています。応募へのハードルが低い分、幅広い層の求職者にアプローチしやすく、母国語でコミュニケーションを取りやすい点も特徴です。
一方で、応募者の質や本人確認の手間が増える場合もあり、採用後の選考フローを丁寧に整えることが求められます。
3.雇用契約の締結
採用が決まったら、雇用契約を結びます。雇用契約は「特定技能雇用契約及び特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令」の第一条に基づいて作成しましょう。また、締結雇用契約書は、外国人が理解できる言語で作成・説明することが必要です。
4.支援計画の準備
- 事前ガイダンス
- 出入国する際の送迎
- 住居確保・生活に必要な契約支援
- 生活オリエンテーション
- 公的手続等への同行
- 日本語学習の機会の提供
- 相談・苦情への対応
- 日本人との交流促進
- 転職支援(人員整理等の場合)
- 定期的な面談・行政機関への通報
特定技能1号を受け入れる場合、企業には「支援計画の策定・実施義務」があります。具体的な支援は以下の通りです。支援を自社で行うのが難しい場合は、登録支援機関に委託できます。
事前ガイダンス
雇用契約締結後、在留資格認定書交付申請前または在留資格変更許可申請前に、労働条件・活動内容・入国手続き・保証金徴収の有無などについて、対面・テレビ電話などで説明
出入国する際の送迎
入国時に空港等と事業所又は住居への送迎、帰国時に空港の保安検査場までの送迎・同行
住居確保・生活に必要な契約支援
連帯保証人になる、社宅を提供するなど、銀行口座等の開設、携帯電話やライフラインの契約等を案内・各手続の補助
生活オリエンテーション
円滑に社会生活を営めるよう日本のルールやマナー、公共機関の利用方法や連絡先、災害時の対応等の説明
公的手続等への同行
必要に応じ住居地・社会保障税などの手続の同行、書類作成の補助
日本語学習の機会の提供
日本語教室等の入学案内、日本語学習教材の情報提供等
相談・苦情への対応
職場や生活上の相談・苦情等について、外国人が十分に理解することができる言語での対応、内容に応じた必要な助言、指導等
日本人との交流促進
自治会等の地域住民との交流の場や、地域のお祭りなどの行事の案内や、参加の補助等
転職支援(人員整理等の場合)
受入れ側の都合により雇用契約を解除する場合の転職先を探す手伝いや、 推薦状の作成等に加え、求職活動を行うための有給休暇の付与や必要な行政手続の情報の提供
定期的な面談・行政機関への通報
支援責任者等が外国人及びその上司等と定期的(3ヶ月に1回以上)に面談し、労働基準法違反等があれば通報
5.在留資格の申請・許可
採用が決まったら、在留資格「特定技能」の申請を行います。在留資格の申請には「外国人本人に関する書類」「受け入れ企業に関する書類」「分野に関する書類」の3つが必要です。
外国人本人に関する書類
- 在留資格認定証明書交付申請書(在留資格変更許可申請書)
- 証明写真
- 特定技能外国人の報酬に関する説明書
- 特定技能雇用契約書の写し(雇用条件書の写し・賃金の支払)
- 雇用の経緯に係る説明書
- 徴収費用の説明書
- 健康診断個人票
- 受診者の申告書
- 1号特定技能外国人支援計画書
外国人本人に関する書類で必要なものは上記の通りです。海外在住の外国人を採用する場合は「在留資格認定証明書交付申請書」、日本在住の外国人を採用する場合は「在留資格変更許可申請書」が必要となります。
また、特定の国籍の外国人を採用する場合や、支援計画の実施を全て登録支援機関に委託する場合は追加で書類が必要です。
受け入れ企業に関する書類(法人の場合)
- 特定技能所属機関概要書
- 登記事項証明書
- 業務執行に関わる役員の住民票の写し
- 特定技能所属機関の役員に関する誓約書
- 労働保険料等納付証明書
- 直近1年間の法人住民税の市町村発行の納税証明書
- 社会保険料納入状況回答票または健康保険・厚生年金保険料領収証書の写し
- 税務署発行の納税証明書
受け入れ企業に関する書類は上記のとおりですが、必要なものは法人か個人か、また過去の受け入れ実績の有無によって異なります。詳細は最新の要件を踏まえ、出入国在留管理庁の公式サイトで確認しておくと安心です。
手続きが複雑に感じる場合は、登録支援機関に代行してもらうことも可能です。申請書類の作成や提出、支援計画の報告まで一括で任せられるため、初めて特定技能を受け入れる企業にもおすすめです。
分野に関する書類
分野に関する書類は、該当分野の技能検定に合格していることを証明する「合格証明書の写し」や、特定技能外国人の受け入れに関する誓約書、事業所の概要書などが求められます。
必要となる書類は分野や受け入れ条件によって大きく異なるため、最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトで確認しておくことが大切です。
6.入社・定着支援
在留資格が許可され、入国・入社した後も企業には継続的な支援義務があります。定期面談や気軽に相談できる体制を整え、特定技能外国人が働きやすい環境を作りましょう。
【PR】特定技能外国人の採用・派遣ならグロップにおまかせ
- 人材ビジネスにおける豊富な実績と経験がある
- 募集~入国後の支援までワンストップ対応が可能
- 質の高い教育ができる
- 法令遵守の適切な管理
- 働く外国人に寄り添った丁寧な支援
グロップは、特定技能外国人の募集から面接、入国前準備、入国後の生活・就業支援までを自社グループ内で一貫対応しています。外部委託に頼らず社内で完結させることで、スムーズで質の高い支援が可能です。
また、人材ビジネスで培った豊富な実績と経験をもとに、法令を遵守した適切な管理を行います。教育にも力を入れており、日本語だけでなく社会人としてのマナーや安全衛生管理など、実務に役立つ幅広い内容を教えています。
外国人一人ひとりに寄り添う丁寧なサポートを行い、安心して長く働ける環境づくりを支援しています。特定技能の採用をお考えなら、グロップまでお気軽にご相談ください。
特定技能外国人の採用時に注意すべきポイント

- 試験の合格証明
- 契約条件
- 協議会の加入
試験の合格証明
特定技能外国人を採用する際は、特定技能評価試験と日本語能力試験の両方に合格しているかを確認しなければなりません。どちらか一方でも未合格だと、在留資格「特定技能」を申請できないからです。
特定技能評価試験は、介護や外食、建設など分野ごとに実施される技能試験で、合格した分野でのみ就労できます。面接時には合格証明書を提出してもらい、試験の分野が自社の業務内容と一致しているかを確かめましょう。
日本語能力については、日本語能力試験(JLPT N4以上)またはJFT-Basic(A2レベル)のどちらかが必要です。証明書の原本を確認し、コピーを保管しておくと安心です。
契約条件
特定技能外国人を採用する際は、日本人と同等以上の労働条件で契約を結ぶことが前提です。特定技能の在留資格は「労働者」として認められる制度のため、不当な低賃金や不利な待遇は許されません。
雇用契約では、賃金・勤務時間・休日・福利厚生などを明確にし、日本人社員と同水準の条件であることを確認する必要があります。特に賃金は、基本給だけでなく各種手当も含めた総支給額で比較されます。
また、パートタイムや短時間雇用は原則として認められていません。 特定技能の就労は「フルタイムで安定的に働くこと」が前提とされており、週30時間未満などの契約では在留資格が下りないケースがあります。
協議会の加入
特定技能外国人を受け入れる企業は、原則として「特定技能所属機関等協議会」(以下、協議会)に加入する義務があります。
この協議会は、法務省・出入国在留管理庁のもとで設置された組織で、外国人材の受け入れを適正に行うために、所属機関(受入れ企業)や登録支援機関が情報共有や改善活動を行う場です。
協議会への加入は、特定技能1号の外国人を受け入れる場合にほぼ必須とされています。加入していない企業は、在留資格の申請段階で「受入れ機関」として認められない、または申請が受理されない場合があります。
特定技能外国人の採用パターンは大きく3つ
国内在留者の採用
すでに日本に住んでいる特定技能人材や、技能実習を修了して特定技能へ移行したい人材を採用する方法です。日本語でのコミュニケーションが比較的スムーズで、生活環境の立ち上げ負担も少なく、入社までの期間が短いという特徴があります。
急ぎで即戦力を確保したい企業にとって、最もスピーディーで実務上のハードルが低い採用パターンです。
海外からの採用
送り出し機関や紹介会社と連携して、現地で候補者を選考する方法です。国内採用と比べて候補者数が多く、若手や将来性のある人材を確保しやすいという利点があります。
一方で、入国までには手続きやビザ申請などの時間を要するため、受け入れまでに数か月の準備期間が必要になります。長期的な採用計画を立てている企業や、継続して人材を確保したい企業に向いています。
技能実習2号修了者の移行採用
技能実習を修了した人材を特定技能として採用する方法は、企業側にとって最もミスマッチが起こりにくい採用パターンです。実習生として既に業務を経験しているため、現場の作業にすぐに馴染み、即戦力として活躍しやすいという強みがあります。
また、一部の分野では技能試験や日本語試験が免除されるため、移行手続きも比較的スムーズです。実習期間中に優秀だった人材を長期雇用したい企業に適しています。
特定技能外国人の採用にかかる費用相場

| 項目 | 費用相場 |
|---|---|
| 送り出し機関への手数料 | 20〜60万円 |
| 人材紹介の手数料 | 30~60万円 |
| 在留資格申請・手続き費用 | 10万〜30万円 |
| 登録支援機関への支援委託費用 | 月額3万〜5万円/人 |
| 渡航費(航空券など) | 5万〜10万円 |
| 住居の初期費用 | おおよそ家賃4.5~5ヶ月分 |
| 在留期間更新申請に関する委託費用 | 4〜10万円 |
特定技能外国人の採用には、在留資格の申請や支援体制の整備など、さまざまな費用が発生します。ベトナム、カンボジア、ミャンマー、フィリピンから採用する場合は、現地の送り出し機関を通す必要があり、その手数料として20万〜60万円程度かかります。
一方で、すでに日本に在留している外国人を採用する場合は、送り出し機関への手数料や渡航費、住居の初期費用が不要なため、初期コストを抑えることが可能です。採用ルートによって費用が大きく変わる点を踏まえて、事前に採用計画を立てておきましょう。
特定技能の採用に関するよくある質問
特定技能外国人の採用にはどのくらい期間がかかる?
書類準備や在留資格申請に1〜3ヶ月程度かかるのが一般的です。海外から呼ぶ場合は渡航準備も含めてさらに時間が必要なため、余裕を持ったスケジュールを組みましょう。
協議会への加入は必須?
特定技能1号を受け入れる企業は「特定技能所属機関等協議会」への加入が原則必要です。加入しないと受入れ機関として認められない可能性があります。
支援計画は必ず自社でやらないといけない?
いいえ、登録支援機関に委託することも可能です。予算や人員リソースを踏まえて検討しましょう。
まとめ:特定技能外国人の採用は業者にまかせるのがおすすめ
特定技能外国人の採用は、制度や手続きが複雑で、必要な書類や条件も分野によって異なります。誤った手続きをすると、在留資格が下りなかったり、受入れ機関として認められないリスクもあります。
初めて採用する企業や人事担当者は、専門の登録支援機関や人材紹介会社に任せるのがおすすめです。


