技能実習生と特定技能10の違い!どちらの外国人材を選ぶべきか徹底解説
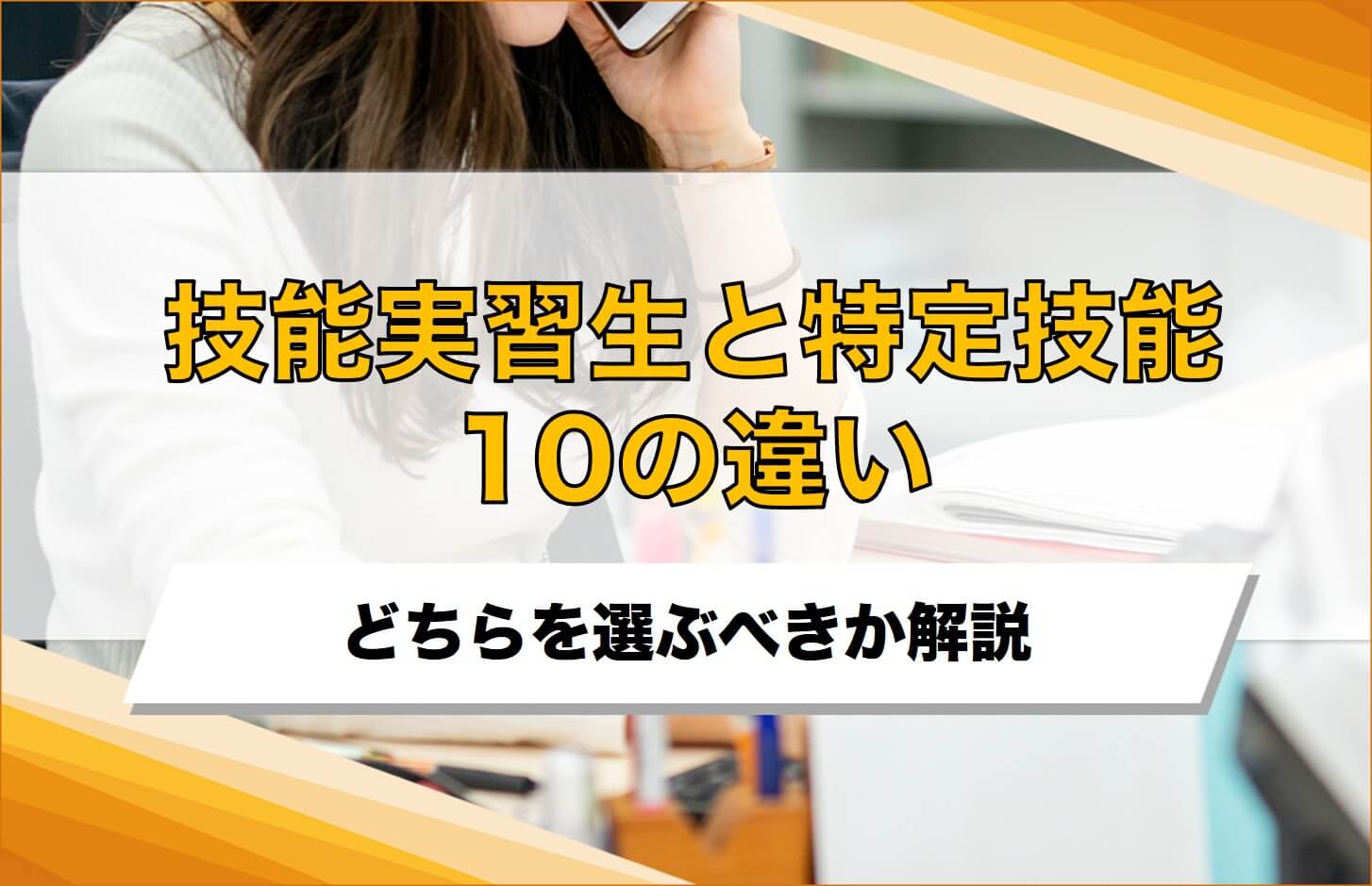
「技能実習と特定技能の違いは?」
「どちらの外国人材を選ぶべき?」
現在の日本企業の人材不足を補っているのは「技能実習」や「特定技能」などの制度による外国人材です。制度をうまく利用することで、採用コストを抑えながら人材を受け入れたい・長期的に即戦力人材を雇用したいなど、自社の希望に合った外国人材を確保できます。
しかし、技能実習と特定技能では目的や条件などが大きく異なります。2つの制度の違いが分からず、利用を迷っている方も多いのではないでしょうか。
そこで本記事では、技能実習と特定技能の違いや企業にとってどちらがおすすめなのかを解説します。利用を検討している企業は参考にしてください。
目次
技能実習と特定技能の違い比較表
| 在留資格 | 技能実習 | 特定技能1号 |
|---|---|---|
| 目的 | 技術移転による 発展途上国への国際協力 |
人手不足の解消 |
| 在留期間上限 | 1号:1年、2号:2年、3号:2年 | 5年 |
| 技能水準 | なし | 相当程度の知識又は経験が必要 |
| 日本語 能力水準 |
なし | ある程度の日常会話 |
| 入国時の試験 | なし | 技能・日本語能力を試験棟で確認 (技能試験※職種ごと) |
| 監理・ 支援 |
監理あり(監理団体) | 支援あり(受入れ機関・登録支援機関) |
| 雇用形態 | 直雇のみ | 原則直雇のみ(農業・漁業は派遣可能) |
| 採用 ルート |
監理団体を通じて海外からのみ | 多様な採用ルートあり・国内外で採用可能 |
| 受け入れ 可能人数 |
制限あり | 制限なし |
| 転職 | 原則不可(帰国不可) | 可能(転職先の業務区分による) |
技能実習と特定技能の違いは主に10あります。それぞれ詳しく解説していきます。
目的
技能実習と特定技能は、制度の目的が大きく異なります。技能実習は、日本の技術を発展途上国へ普及させることで、国際貢献を目的として設けられた在留資格です。
一方で特定技能は、日本国内の人手不足を補うための労働力の確保を目的とした在留資格となっています。
在留期間上限
技能実習の在留期間は、段階的に延長できる仕組みになっており、1号・2号・3号とステップを踏むことで最長5年間の在留が可能です。それぞれの段階に進むには、技能評価試験などの条件を満たす必要があります。
一方で、特定技能は1号の在留期間を更新することで通算5年間の在留が可能です。さらに条件を満たして2号に移行すれば、在留期間の上限はなく、長期的に日本で働き続けることもできます。
技能水準
技能実習は、日本の技術を発展途上国へ普及させ国際貢献することを目的とした制度のため、入国前に特定の技能を習得している必要はありません。一方で、特定技能は1号・2号ともに、就労する分野で一定水準以上の知識や経験が必要です。
日本語能力水準
技能実習は、受け入れ企業での研修を通じて日本語や技能を習得する制度のため、入国時点では日本語力が求められません。
一方、特定技能の在留資格を取得するには、日本語能力試験(JLPT)N4以上に合格することが基本条件とされています。仕事の内容や安全管理を理解できる程度の日本語コミュニケーション能力が必要とされるためです。
入国時の試験
技能実習生は、入国時の試験はありません。現場での研修や生活を通じて日本語や技能を学び、段階的に成長していく仕組みです。
特定技能は、人手不足を補う労働力の確保が目的のため、「技能評価試験」と「日本語能力試験」の合格が条件です。例えば、介護分野で働く場合は「介護技能評価試験」に合格していなければなりません。
監理・支援
技能実習では、監理団体が実習生の受け入れを仲介し、実習の指導や監督を担います。
一方、特定技能では、受入れ企業が自ら外国人の生活支援や日本語学習支援を行うか、または登録支援機関に委託してサポートを受ける形になります。このように、支援の主体が異なる点が両制度の大きな違いです。
雇用形態
技能実習は、あくまで技能の習得を目的とした研修制度です。企業とは雇用契約を結びますが、目的は「労働」ではなく「教育・訓練」にあるため、残業や実習計画にない業務を行わせることは認められていません。
一方、特定技能は労働力としての就労を前提とした在留資格です。受入れ企業と直接雇用契約を結び、日本人と同等以上の賃金・労働条件で働きます。
採用ルート
技能実習は、基本的に監理団体からの紹介でしか受け入れることができません。一方、特定技能は受け入れ企業自ら採用を行うことや、紹介会社の利用が可能です。
しかし、特定技能の場合、海外在住者の採用において認定送り出し機関の利用が義務付けられている国や独自ルールがあるので注意が必要です。
受け入れ人数
技能実習は、企業の常勤職員数に応じて受け入れ人数の上限が決められています。例えば、職員が30人以下の企業では最大3人までなど、指導体制を確保するための制限があります。
一方、特定技能には人数制限が基本的に設けられていません。人手不足を補う即戦力人材の確保が目的のため、企業の規模にかかわらず柔軟に受け入れることができます。ただし、介護や建設など一部の分野では、別途制限が設定されています。
転職
技能実習は、受け入れ先の企業で技能を習得することを条件に在留が認められるため、原則として転職できません。特定技能は、就労なので同一の職種であれば転職が可能です。
特定技能で他職種に転職する場合は、当該職種での特定技能試験に合格する必要があります。
技能実習は特定技能に移行できる

技能実習は、一定の条件を満たせば特定技能へ移行できます。条件とは「技能実習2号を良好に修了していること」「技能実習の職種・作業内容が特定技能1号の業務と関連していること」の2つです。
また、技能実習を良好に修了し、職種と業務内容に関連性がある場合は、技能試験と日本語試験が免除されます。ただし、異なる分野で働きたい場合は、新たに特定技能試験に合格する必要があります。
実習中に問題行動があると移行が難しい
実習中に問題行動があると「良好な修了」が認められず移行が難しいです。法令違反は当然のことながら「指示に従わない」「無断欠勤を繰り返す」「技能実習の目的から逸脱した行為」などが問題行動に該当します。
一方で、実技試験に合格していなくても、出勤状況や技能の修得状況・生活態度などをまとめた評価調書により、良好な修了と判断されるケースもあります。実習中の姿勢こそが、特定技能への移行を左右する重要なポイントです。
すべての分野で移行できるわけではない
技能実習生から特定技能への移行は、すべての職種・作業が対象となるわけではありません。特定技能制度は、人手不足が深刻な一部の分野(例:建設、介護、外食、製造業など)に限定されているため、実習で行っていた業務内容によっては移行が認められないケースがあります。
例えば、繊維・衣服、印刷、リネンサプライ業務などの分野は対象外です。そのため、受け入れ企業は「自社の実習職種が特定技能の対象分野に該当するか」を事前に確認したうえで採用計画を立てることが重要です。
企業は技能実習と特定技能どっちを選ぶべき?

技能実習がおすすめなケース
技能実習は、採用コストを抑えたい企業におすすめです。業務期間が3〜5年と限定されており、特定技能に比べて初期費用や給与水準が低いためコストを抑えられます。技能実習生は、来日が初めての人材を受け入れることが多く、採用候補者を見つけやすいのもメリットです。
また、既に監理団体とのつながりがあり受け入れ体制が整っている企業や、教育・CSR的な側面を重視して「国際貢献」を打ち出したい企業にもおすすめでしょう。
特定技能がおすすめなケース
特定技能は、長期的に即戦力人材を雇用したい企業にぴったりです。技能試験や日本語試験に合格した人材を採用できるため、入社後すぐに現場で活躍できます。
家族帯同による安定した就労を望む人材も多く、長期的な定着が見込めます。さらに、企業が直接雇用契約を結ぶ仕組みのため、労務管理や生活支援を自社で一貫して行える点もメリットです。
技能実習と特定技能に関するよくある質問
技能実習と特定技能の一番大きな違いは?
大きな違いは制度の目的です。技能実習は日本の技術を発展途上国に普及させることが目的ですが、特定技能は人手不足を補うための労働力の確保を目的とした制度です。
登録支援機関と監理団体の違いは?
支援する在留資格と業務内容が異なります。登録支援機関は、特定技能外国人を対象に職場や社会生活など日本で暮らすための補助が主な役割です。監理団体は、技能実習生を対象に技能実習制度の適正な運営ができているかの監査や支援を行っています。
技能実習と特定技能の併用はできる?
技能実習と特定技能の併用はできません。しかし、技能実習を修了した外国人が特定技能へ在留資格を変更することは可能です。
まとめ:技能実習と特定技能の違いを理解した上で検討すべき
特定技能と技能実習は、在留期間の上限や求められる技能水準・日本語能力水準など、さまざまな点で違いがあります。それぞれのメリット・デメリットを比較し、自社に合った外国人材の受け入れ方法を選択しましょう。
グロップは、特定技能外国人の募集から面接、入国前準備、入国後の生活・就業支援までを自社グループ内で一貫対応しています。外部委託に頼らず社内で完結させることで、スムーズで質の高い支援が可能です。特定技能の採用をお考えなら、グロップまでご相談ください。


