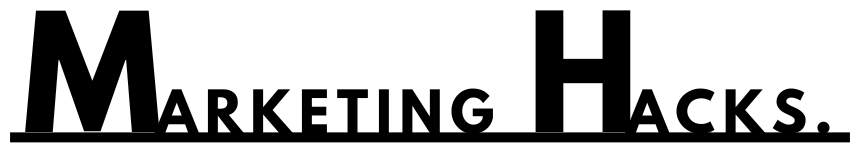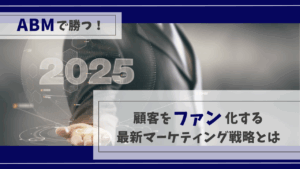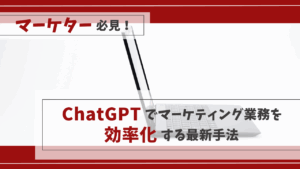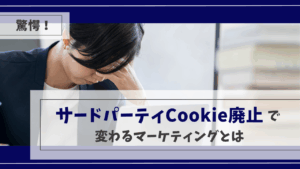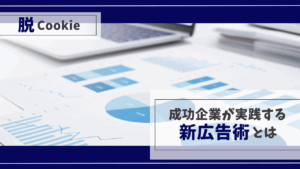短尺動画マーケティングが注目を集める中、15秒程度の動画で問い合わせ数を効果的に増やす方法をご存知でしょうか?本記事では、企業のマーケティング担当者が実践できる短尺動画の効果的な活用法と成功事例を紹介します。
短尺動画の力に気づいていますか?

マーケティング担当者として、「新しい施策を打ち出したいけれど何が効果的なのか分からない」「限られた予算の中で最大の効果を出したい」というお悩みはありませんか?
現代のデジタルマーケティングにおいて、短尺動画はますます重要な役割を果たしています。実際に適切に活用することで問い合わせ増加に効果があることが複数の事例で確認されています。
例えば、ある工務店では短尺動画の活用により問い合わせが「前月比で3倍に増加」したという事例があります。
また、大手家具メーカーのニトリではTikTokを活用した短尺動画マーケティングにより、若年層の「来店数が施策実施前比で2倍に上昇」したという実績も報告されています。
この記事では、なぜ短尺動画が効果的なのか、成功事例から学ぶポイント、効果的な動画制作テクニック、効果測定の方法、そして明日から実践できるアクションプランまで、幅広く解説します。
\お問い合わせはこちらから /
なぜ短尺動画が効果的なのか?

「なぜそんな短い動画で効果が出るの?」と疑問に思われる方も多いでしょう。実は、現代の消費者行動と短尺動画の特性が合致していることが、その効果の理由なのです。
「タイパ」志向の高まり
現代の消費者、特にZ世代を中心に、時間を効率的に使おうとする「タイパ(タイムパフォーマンス)」思考が強まっています。これは、短時間で確実な結果(面白さ・発見・共感・感動)を求める傾向のことです。
P-Tipsによると、タイパとは「時間をどれだけ効率的に使えるか、一定の時間で成果をどれだけ高めることができるかを示す言葉」と定義されており、現代の若者の価値観を反映しています。
自分にとって魅力的な情報を効率的に消費し、限られた時間内で最大の満足を得ようとする考え方が広がっており、短尺動画はこのニーズにマッチしているのです。
視覚的・感覚的な訴求力
短尺動画の成功の鍵を握るのは、冒頭の数秒間です。この短い時間で視聴者の興味を引かなければ、すぐにスキップされてしまいます。
TikTokやInstagramリールなどのプラットフォームでは、ユーザーは動画をスワイプするだけで簡単にスキップできます。そのコンテンツが面白くないと判断されれば、すぐに離脱されてしまうのです。
動画の冒頭が視聴者の視聴継続判断に非常に重要であることは複数の情報源で確認されています。
スマホ時代の情報消費スタイル
スマートフォンが普及した現代では、情報の消費スタイルが大きく変化しました。通勤中や休憩時間など、すきま時間に短い動画をサクッと見る習慣が定着しています。
短尺動画はこのような現代人の情報消費スタイルに適しているのです。
競合との差別化ポイント
まだ多くの企業が短尺動画マーケティングを十分に活用できていません。だからこそ、今取り組むことで競合他社との差別化が可能です。
短尺動画を戦略的に活用することで、ブランドの個性を効果的に表現し、競合他社と一線を画すことができるのです。
成功事例から学ぶ効果的な短尺動画

「具体的にどんな動画が効果を上げているの?」という疑問にお答えするため、実際に短尺動画を活用して成功を収めた企業の事例をご紹介します。
事例1:SMRJ「社畜ミュージアム」の共感戦略
中小企業基盤整備機構(SMRJ)は、自社のミッションである「働く人をもっと笑顔に」「日本の中小企業を支えたい」という思いを伝えるショート動画を制作しました。
残業続きの社畜社員の悲哀を美術館の展示品に見立てて表現した動画は、思わずクスッと苦笑してしまう内容が働く人々の共感を集めました。
CAREARC BLOGによると、この動画はSNS等で200万回以上再生され、SMRJへの問い合わせ増加に貢献したことが報告されています。
この事例から学べるのは、ターゲットの共感を得られるストーリー設計の重要性です。短い時間でも視聴者の心を掴むストーリーは強力なマーケティングツールになります。
事例2:ニトリのインフルエンサー活用法
TikTok Ads Businessの公式ブログによると、ニトリは新生活に向けた買い揃え需要が高まる3月に合わせ、インフルエンサーを活用したショート動画マーケティングを実施しました。
静止画のみでは魅力が伝わりにくい「シングルマットレス」「デスクプレフェセット」などの商品を、TikTokクリエイターに使用してもらい、生活者目線でのリアルな使用感や活用ポイントを動画で紹介。この施策により、若年層の来店数が実施前比で2倍に上昇したことが報告されています。
この事例からは、商品の魅力を伝えるには実際の使用シーンを見せることが効果的であることが分かります。また、ターゲット層に合わせたプラットフォーム選定の重要性も教えてくれています。
事例3:工務店の問い合わせ増加事例
shortvideo.jpのブログによると、ある工務店では、ショート動画の活用により問い合わせが前月比で3倍に増加した事例があります。
注文住宅のアピールにショート動画を活用し、見学会情報や施工例を短時間で魅力的に伝えることで、若い世代の顧客獲得に成功しました。
静止画では伝わりにくい住宅の空間の広がりや光の入り方、生活動線などを短尺動画で効果的に表現したことが成功の要因でした。
各事例から導き出せる成功の共通点
これらの事例から見えてくる成功の共通点は以下の通りです:
1. ターゲットに刺さるメッセージ設計:視聴者の共感を得られる内容になっている
2. 目的の明確化:問い合わせ増加や来店促進など、目的を明確にした上で内容を設計している
3. 商品やサービスの魅力を短時間で伝える工夫:静止画では伝わりにくい部分を動画の特性を活かして表現
4. 適切なプラットフォーム選択:ターゲット層が多く利用するプラットフォームを選んでいる
5. 親近感の創出:実際の使用シーンや共感できる内容を取り入れることで親近感と信頼性を高めている
\ お問い合わせはこちらから /
効果的な短尺動画制作テクニック

「でも、動画制作なんて難しそう…」と思われるかもしれませんが、基本的なテクニックを押さえれば、マーケティング担当者の方でも効果的な短尺動画を作ることができます。
フックを意識した構成の作り方
冒頭に視聴者の心を掴むフックを入れることが重要です。キャッチーな音楽や効果音、インパクトのあるビジュアル、ターゲットへの呼びかけといった、つい手を止めてしまうような仕掛けが効果的です。
例えば:
・キャッチーなフレーズやテキスト
・意外性のある映像や音楽
・視聴者の悩みを直接言語化する質問
・ユーモアのある演出
冒頭で視聴者の注目を集められなければ、残りの内容はほとんど意味を持ちません。最も伝えたいことを最初に持ってくる「逆ピラミッド構造」を意識しましょう。
テキストの効果的な活用テクニック
短い尺のショート動画は、通勤中など音声をオフにした状態で視聴している人も多くいます。BGMやナレーションを聞いていなくても、おおまかな内容が理解できるように、テキストを入れるタイミングや映像の流れを工夫しましょう。
テキストの位置や内容、色やフォントも重要なポイントです。バックに流れる動画の見やすさを考えるだけでなく、企画やコンセプトに合ったものに統一することで効果的なメッセージ伝達が可能になります。
具体的なテクニック:
・背景との色のコントラストを意識する
・読みやすいフォントを選ぶ
・1画面に表示する文字数を制限する
・重要なキーワードは大きく表示する
・テキストアニメーションを活用する
スピード感のある編集方法とコツ
短尺動画にはテンポの良さが大切です。短い尺の中でもテーマを伝えきれるよう、動画の流れやストーリーを工夫しましょう。スピード感を持たせるために、あえてナレーションや映像を倍速再生にするのもひとつの方法です。
編集のコツ:
・カット割りを多めにして、テンポよく場面を切り替える
・重要なメッセージは尺を長めに、不要な間は削る
・音楽のビートに合わせてカットを切り替える
・ズームイン・ズームアウトなどの動きを入れる
トレンドを取り入れた話題性の作り方
プラットフォーム上のトレンドを積極的に活用することで、リーチを最大化することが可能です。
流行のハッシュタグやチャレンジ企画に参加することで、自然とアルゴリズムに乗りやすくなり、より多くのユーザーにコンテンツを届けることができます。
また、自社商品やサービスを絡めたオリジナルのハッシュタグチャレンジを企画することでUGC(ユーザー生成コンテンツ)を促進し、拡散効果を高めることもできます。ただしトレンドを取り入れる際は、自社ブランドとの親和性を考慮することも念頭に置いておきましょう。
初心者でも使いやすい動画編集ツール紹介
動画編集が初めての方でも簡単に使えるツールがたくさんあります:
・CapCut:TikTok運営元が提供する無料アプリ。テンプレートが豊富で初心者でも簡単に作成可能
・Adobe Express:テンプレートを活用してプロ級の動画を簡単に作成できる
・InShot:シンプルな操作性で直感的に編集できる人気アプリ
・iMovie:Apple製品ユーザーなら無料で使える高機能エディタ
・Canva:静止画だけでなく動画も作成できる人気ツール
これらのツールを活用すれば、専門的な知識がなくても効果的な短尺動画を作成することができます。まずは簡単なものから試してみましょう。
効果測定と改善サイクル

「動画を作っただけで終わり」にならないためには、効果測定と継続的な改善が欠かせません。マーケティング担当者として、PDCAを回す習慣を身につけましょう。
押さえるべき効果測定の基本指標
効果測定には以下のような指標を活用しましょう:
・視聴回数・再生完了率:再生数そのものや、どのくらいの人が最後まで見てくれたか
・クリック率(CTR):動画からプロフィールやリンクへのクリック率
・エンゲージメント:いいね・コメント・シェア数の推移
・コンバージョン数:設定したCV(問い合わせや購入など)につながった数
特に「視聴者がどの時点で動画から離脱したか(スキップ率)」のデータは貴重です。例えば多くのユーザーが特定の時点で離脱しているなら、その部分に改善の余地があると考えられます。
PDCAサイクルの具体的な回し方
効果的な改善サイクルのためにPDCAを回しましょう:
1. Plan(計画):分析から得られた発見を踏まえ、次の動画の企画を練る
2. Do(実行):新たな動画を制作し投稿する
3. Check(評価):データを収集し、改善点を探る
4. Act(改善):成果の良かった手法は継続し、悪かった部分は修正する
このサイクルを回すことで、ショート動画マーケティングの効果が徐々に高まっていきます。「うまくいかなかった」としても、それは貴重な学びのチャンス。
何が効果的で何が効果的でなかったかを客観的に分析し、次の施策に活かしましょう。
A/Bテストの効果的な実施方法
同じ商品やサービスの短尺動画でも、異なるアプローチで複数パターン作成してテストすることで、どのような要素が効果的かを検証できます。
A/Bテストのポイント:
・テストする要素を1つに絞る(冒頭のフック、BGM、テキストの量など)
・十分なサンプル数を確保する
・同じ条件(曜日・時間帯など)で配信する
・データを正確に計測する
・結果から学びを抽出し次のコンテンツに活かす
例えば、同じ商品の紹介動画でも「ユーモア系の導入」と「データ重視の導入」で2パターン作り、どちらが視聴完了率やクリック率が高いかを検証するといった方法が効果的です。
視聴者離脱ポイントの分析と改善策
多くのプラットフォームでは、視聴者がどの時点で動画を離脱したかを示すデータを確認することができます。このデータは非常に貴重な情報源です。
離脱ポイントが多い場所があれば、そこに問題がある可能性が高いです。例えば:
・冒頭で大量の離脱がある → フックが弱い
・中盤で離脱が増える → テンポが悪い、または内容に飽きられている
・終盤直前の離脱 → CTAが弱い、または期待と内容のギャップがある
それぞれの離脱ポイントに合わせて改善策を考えましょう。
明日から実践!問い合わせ増加のポイント
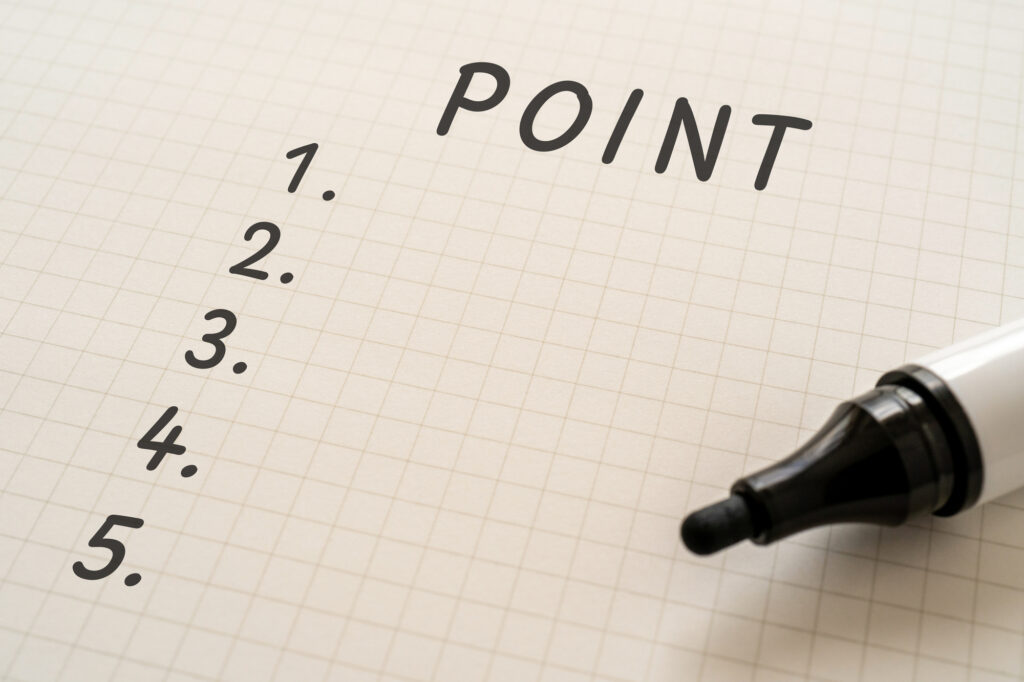
「実際に明日から何をすればいいの?」という疑問にお答えするため、すぐに実践できるポイントをご紹介します。
ターゲットに合わせたプラットフォーム選定方法
ターゲット層に合わせて最適なプラットフォームを選びましょう。例えば:
・Instagram:女性の利用率が高く、「化粧品」「ファッション関連」「外食店舗」のジャンルに強み
・TikTok:Z世代を中心に高い人気があり、幅広いジャンルに対応
・YouTube Shorts:より幅広い年齢層にリーチでき、教育コンテンツやハウツー系に強み
・Twitter/X:情報拡散力が高く、トレンドや時事ネタと組み合わせやすい
ターゲットの年齢層や性別、興味関心に合わせて最適なプラットフォームを選定しましょう。また、複数のプラットフォームを横断的に活用することで、相乗効果を生み出すことも可能です。
親近感を生み出す工夫と実例
ショート動画を最後まで視聴してもらい、問い合わせなどのアクションにつなげるためには親近感が重要です。スタッフや社員に出演してもらい、いわゆる「中の人」の存在を感じられるコンテンツにすると親近感が生まれます。
具体的な工夫例:
・社員のリアルな声や表情を見せる
・オフィスや工場などの普段見られない裏側を紹介する
・失敗談やNG集など、人間味のある内容を取り入れる
・お客様の声を紹介する
・質問に答える形式のQ&A動画を作る
また、お堅いイメージがある企業の場合、親近感のあるテーマでショート動画を制作すれば、良い意味で期待を裏切ることができ、強い印象を残せます。
最適な投稿頻度と継続性の保ち方
ショート動画は頻繁に制作・投稿することでより効果を発揮します。多くの動画を投稿することで視聴者に見てもらえるチャンスが増え、また多くのプラットフォームでは高頻度で投稿していると、動画やチャンネルの評価も高まる傾向があります。
ただし、低品質な動画を量産するのは逆効果なので、最初は投稿頻度よりも動画のクオリティを高めることを優先しましょう。徐々に投稿頻度を上げていくことが理想的です。
継続のためのコツ:
・制作フローを標準化する
・撮影から編集までの役割分担を明確にする
・コンテンツカレンダーを作成する
・素材のストックを常に持っておく
・バッチ処理(まとめて撮影・編集)を活用する
最初は週1回の投稿からスタートし、慣れてきたら週2~3回に増やすなど、段階的に頻度を上げていくのがおすすめです。
明確なコール・トゥ・アクション(CTA)の設置方法
問い合わせ数を増やすためには、明確なCTAを入れることが不可欠です。
例えば「最後に画面いっぱいのCTAテキストを表示してタップ誘」「矢印やサークルで問い合わせボタンを強調」などの工夫をしましょう。
効果的なCTAの例:
・「詳しくはプロフィールのリンクから」
・「公式サイトで限定特典をチェック」
・「今だけの特別割引はこちら」
・「無料相談はDMから」
・「コメント欄に質問をどうぞ」
動画の最後には必ず視聴者に次の行動を促すメッセージを入れましょう。そうすることで、単なる視聴で終わらせずに、具体的なアクションにつなげることができます。
\お問い合わせはこちらから /
短尺動画で問い合わせ増加を実現しよう

いかがでしたか?短尺動画を効果的に活用することで、問い合わせを増やすことができます。最後に、この記事のポイントをまとめましょう。
記事全体のポイント整理
1. 短尺動画が効果的な理由:「タイパ志向」の高まり、視覚的・感覚的訴求力の強さ、冒頭の重要性など、現代の消費者行動と短尺動画の特性が合致している
2. 成功事例から学ぶポイント:共感を生むストーリー、リアルな使用感の紹介、親近感のある内容が効果的
3. 効果的な短尺動画制作テクニック:冒頭のフック、テキストの効果的活用、スピード感のある編集、トレンドの活用がポイント
4. 効果測定と改善サイクル:適切な指標でデータを収集し、PDCAを回して継続的に改善することが重要
5. すぐに実践できるポイント:ターゲットに合わせたプラットフォーム選定、親近感を生み出す工夫、投稿頻度と継続性の維持、明確なCTAの設置が大切
すぐに実践できる3つのアクションステップ
1. まずは自社にあった短尺動画の企画を立てる
・ターゲットのペルソナを明確にする
・伝えたいメッセージを1つに絞る
・視聴者の興味を引くフックを考える
2. 簡単な動画から試作して反応を確認する
・高価な機材は不要、スマートフォンでも十分
・既存の素材(写真や静止画)を活用する
・無料の編集ツールを使って短尺動画にまとめる
3. データを基に改善しながら継続的に発信する
・視聴データを分析して改善点を見つける
・成功したコンテンツの要素を次に活かす
・一定の頻度で継続的に発信する
短尺動画マーケティングはまだ発展途上の分野です。だからこそ、今取り組むことで他社との差別化が可能になります。失敗を恐れず、まずは小さく始めて、データを見ながら改善していくことが大切です。
マーケティング担当者として、この新しいツールを活用することで、自社の問い合わせ数増加に貢献するだけでなく、あなた自身のスキルアップにもつながります。ぜひ明日から実践してみてください。
\ お問い合わせはこちらから /